
階段移動が安全に!松葉杖に代わるアイウォークフリーの使い方を理学療法士が指導
2025年10月1日
松葉杖を使用している方にとって、最も困難で危険な動作の一つが階段の昇降です。「松葉杖で階段を上がるのが怖い」「手すりが使えないから不安」といった声を、理学療法士として臨床現場で数多く聞いてきました。
松葉杖での階段移動は転倒リスクが高く、実際に階段での転落事故により重篤な二次外傷を負う患者様を何度も診てきた経験があります。本記事では、松葉杖での階段移動の危険性と、革新的な解決策であるハンズフリー松葉杖「アイウォークフリー」による安全な階段移動について詳しく解説いたします。
目次
1. 松葉杖での階段移動が危険な理由
2. 松葉杖階段移動時の事故統計と実態
3. 従来の松葉杖階段移動の正しい方法と限界
4. アイウォークフリーによる階段移動の革新性
5. 理学療法士が指導する安全な階段移動法
6. アイウォークフリー使用時の注意点
7. 症例別の階段移動指導
8. まとめ
1. 松葉杖での階段移動が危険な理由
バランス制御の困難さ
理学療法士として分析する松葉杖階段移動時の生体力学的問題:
重心制御の複雑さ:
- 三点支持から二点支持への移行時の不安定性
- 前後方向の重心移動制限
- 左右方向のバランス調整困難
筋協調性の低下:
- 健側下肢への過度な負担
- 体幹筋群の代償的活動
- 上肢筋群の過緊張
手すり使用の制限
両手占有による問題:
松葉杖使用時は両手がふさがるため、手すりの使用が困難になります。これは以下の深刻な問題を引き起こします:
-安全性の大幅な低下:手すりによる安全確保ができない
- 心理的不安の増大:転倒への恐怖感が移動を制限
- 移動速度の低下:慎重な動作により移動効率が悪化
視覚的制約
足元確認の困難:*
- 松葉杖の位置確認に注意が分散
- 階段の段差確認が不十分
2. 松葉杖階段移動時の事故統計と実態
転倒事故の発生状況
理学療法士として勤務する医療機関での観察データ:
階段での転倒要因(上位3位):
- 松葉杖の滑り・外れ:全体の40%
- バランス失調:全体の35%
- 段差の見誤り:全体の25%
二次外傷の深刻性
階段転倒による典型的な外傷:
- 頭部外傷:最も重篤、生命に関わる場合も
- 上肢骨折:手首、前腕骨折が多発
- 胸腰椎圧迫骨折:高齢者で特に注意
- 元傷の悪化:治療期間の大幅延長
心理的影響
転倒恐怖症の発症:
階段での転倒経験や恐怖感により、以下の心理的影響が現れます:
- 外出頻度の減少
- 社会活動からの離脱
- 抑うつ症状の出現
- 自立性の低下
3. 従来の松葉杖階段移動の正しい方法と限界
標準的な松葉杖階段昇降法
昇段時(上がる時)の基本:
- 健側足から先に上げる
- 松葉杖と患側足を同時に上げる
- 体重を健側足に移す
降段時(下がる時)の基本:
- 松葉杖と患側足から先に下ろす
- 健側足を下ろす
- 合言葉:「良い足から天国へ、悪い足から地獄へ」
理学療法士が指摘する現実的な限界
技術習得の困難さ:
- 複雑な動作パターンの記憶
- 恐怖心による動作の硬直化
- 個人差による習得期間の延長
安全性の限界:
- 完璧な技術でも転倒リスクは残存
- 疲労時や注意散漫時のリスク増大
- 緊急時の対応困難
実用性の問題:
- 移動時間の大幅延長
- 精神的ストレスの蓄積
- 日常生活での実用性低下
4. アイウォークフリーによる階段移動の革新性
ハンズフリー設計の優位性
手すり使用の可能性:
アイウォークフリーの最大の革新は、両手が自由になることで手すりが使用できることです。
安全性の飛躍的向上:
- 三点支持の確保:健足、アイウォークフリー、手すり
- バランス制御の向上:手すりによる左右バランス調整
- 心理的安心感:手すりによる安全確保で恐怖心軽減
自然な歩行パターンの維持
生体力学的優位性:
- 正常歩行に近い重心移動パターン
- 健側下肢への負担分散
- 体幹筋群の適切な活用
アイウォークフリーの階段対応仕様
基本スペック(再確認):
- 適応身長:150~195cm
- 本体重量:2.4kg(軽量設計)
- 調整機能:きめ細かいサイズ調整により安定性確保
- 材質:アルミパイプで軽量かつ強度確保
5. 理学療法士が指導する安全な階段移動法
アイウォークフリー装着時の階段昇降指導

昇段時の推奨方法:
- 1. 準備姿勢:手すりを健側手で把持
- 1. 足置き:健側足を上段に配置
- 1. 重心移動:手すりとアイウォークフリーで支持しながら体重移動
- 1. 完了:アイウォークフリーを上段に移動
降段時の推奨方法:
- 1. 手すり確保:必ず手すりを握る
- 1. アイウォークフリー先行:アイウォークフリーを下段に配置
- 1. 重心制御:手すりで重心をコントロールしながら移動
- 1. 健足移動:最後に健側足を移動
段階的訓練プログラム
初期段階(病院内):
- 1-2段の低い階段での練習
- 理学療法士の近位監視下での実施
- 手すり使用の徹底指導
中期段階(自宅環境):
- 実際の階段高での練習
- 上下5段程度での反復練習
- 疲労時の対応方法指導
実用段階(社会復帰):
- 様々な階段環境での適応練習
- 緊急時の対応方法の習得
- 自己判断能力の養成
6. アイウォークフリー使用時の注意点
環境的配慮事項
階段の状況確認:
- 手すりの有無:必須条件として確認
- 段差の高さ:15-20cm程度が理想的
- 踏面の奥行き:25cm以上を推奨
- 滑り止めの状態:滑りやすい材質は要注意
天候・時間帯の考慮:
-雨天時:滑りやすさが増大、使用は控えめに
- 夜間:視認性低下により危険度増大
- 混雑時:他者との接触リスク増大
身体的制限事項
使用制限の判断基準:
- バランス能力:片足立ち10秒以上が目安
- 筋力:健側下肢筋力MMT4以上
-認知機能:指示理解と安全判断が可能
- 視力:階段の段差識別が十分可能
7. 症例別の階段移動指導
若年者(学生・働き盛り世代)
特徴と指導ポイント:
- 活動性が高い:早期の実用的移動を希望
- 学習能力が高い:複雑な動作習得が比較的容易
- 社会復帰への焦り:安全性を軽視する傾向に注
指導方針:
段階的な技術習得を重視し、安全確認を徹底させる
中高年者(40-65歳)
特徴と指導ポイント:
- 身体機能の個人差大:個別評価が重要
- 慎重性が高い:恐怖心への配慮が必要
- 実用性重視:日常生活での使い勝手を重要視
指導方針:
十分な練習期間を設け、自信を持てるまで反復指導
高齢者(65歳以上)
特徴と指導ポイント:
- バランス能力低下:転倒リスクが高い
- 筋力低下:疲労しやすい
- 視覚機能低下:段差認識が困難
指導方針:
能力を適正に評価しながら進める。
8. まとめ
理学療法士として多くの松葉杖使用者の階段移動訓練に携わってきた経験から、従来の松葉杖での階段移動は常に転倒という重大なリスクを伴う動作であることを改めて強調したいと思います。
松葉杖階段移動の根本的問題:
- 両手占有により手すりが使用できない
- 複雑な動作パターンによる習得困難性
- 高い転倒リスクとそれによる重篤な二次外傷
- 心理的恐怖による生活の質の低下
ハンズフリー松葉杖アイウォークフリーによる解決:
- 手すり使用可能による安全性の飛躍的向上
- 自然な歩行パターンによる動作習得の容易さ
- 三点支持(健足・アイウォークフリー・手すり)による安定性
- 心理的安心感による積極的な社会参加
特に階段の多い日本の住環境において、アイウォークフリーが提供する「手すりを使える」という機能は、単なる利便性向上を超えた安全性の革命といえます。
ただし、どれだけ優れた歩行補助具であっても、正しい使用方法の習得と安全への意識が不可欠です。使用開始時には必ず理学療法士による適切な指導を受け、段階的な技術習得を心がけてください。
階段移動への不安から外出を控えがちになる方が多い中、アイウォークフリーという選択肢により、より安全で積極的な社会復帰が実現できることを心から願っています。
アイウォークフリーの購入はこちら:
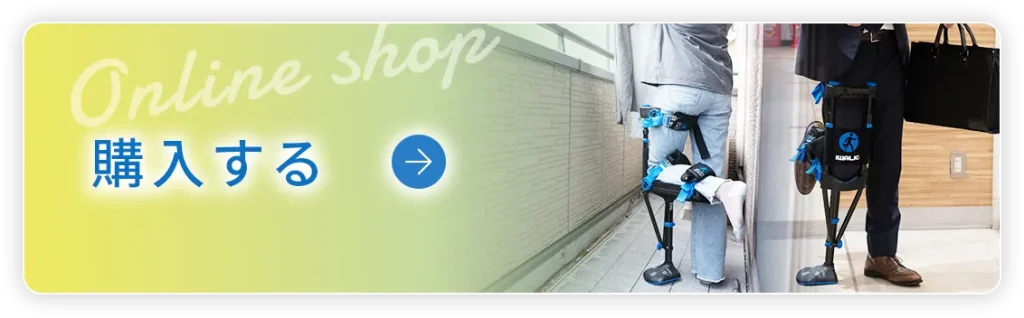
[Amazon公式ページ](https://amzn.asia/d/eAmAa65)
※階段移動の練習は必ず理学療法士の指導のもとで行い、安全を最優先に実施してください。個別の適応については医師にご相談ください。
執筆者紹介
もっこすパパ |理学療法士・ケアマネジャー・公認心理師
理学療法士として15年以上、急性期から回復期、慢性期、在宅医療まで幅広いフィールドで患者支援に従事。整形外科疾患や脳血管障害のリハビリテーションを中心に、実践と研究の両面から機能回復と生活支援を行っている。現在はケアマネジャー・公認心理師としても活動し、多職種連携や地域包括ケアにも精通。医療・福祉の垣根を超えた支援を目指し、専門的な情報をわかりやすく発信している。
